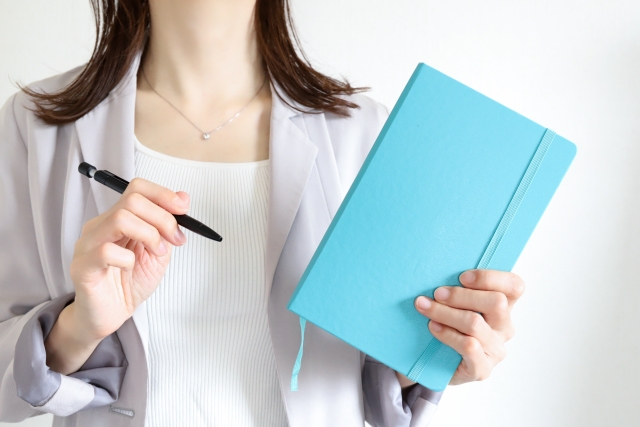子どもたちの成長を見守ってきた私たち親が、その想いを言葉にして届けられるのが「キャリアパスポート」です。
でも、いざコメントを書こうとすると「何を書けばいいの?」と戸惑ってしまうこともありますよね。
この記事では、キャリアパスポートとは何か、なぜ親のコメントが必要なのか、そして書き方や例文までを、やさしく丁寧にご紹介していきます。
キャリアパスポートとは?保護者が知っておきたい基礎知識
キャリア教育とは何か
キャリア教育とは、子どもたちが将来、社会の中で自立し、幸せに生きていくための「生きる力」を育てる教育のことです。
この「生きる力」には、学力だけでなく、考える力、表現する力、他者と関わる力、そして自分自身を理解する力などが含まれます。
自分の得意なことや苦手なこと、興味をもつ分野、挑戦してみたいことなどを通して、「どのように働きたいか」「どんな人生を送りたいか」といった将来像を描けるようになることが目標です。
将来の職業だけでなく、生き方そのものを考える力を養うのが、キャリア教育の大きな目的といえます。
キャリアパスポートの目的と役割
キャリアパスポートは、子どもが小学校から高校まで、学年ごとに自分の目標や取り組みを記録する特別なノートです。
このパスポートには、自分の気持ちや学びの記録、将来に向けた思いなどがつづられます。
学年を重ねるごとに、その内容が積み重なり、子ども自身が自分の変化や成長に気づけるツールとなります。
また、先生や保護者との共有を通じて、周囲の大人が子どもの力をサポートするきっかけにもなります。
子どもの成長と経験の蓄積
キャリアパスポートには、授業や学校行事、日々の活動の中で子どもが「がんばったこと」「うれしかったこと」「悩んだけれど挑戦したこと」などが書き残されていきます。
そうした記録は、その時々の子どもの心の動きや努力を可視化するものであり、あとから見返すことで自信にもつながります。
保護者のコメントは、そうした子どもの経験を受けとめ、励ましの言葉を添える大切な役割を持っています。
子どもの小さな成長も見逃さず、あたたかく見守っていることが伝わるように書いていきましょう。
家庭でのキャリア教育の位置づけ
キャリア教育は、学校の中だけで行われるものではありません。
家庭でも、子どもと一緒に話す時間、体験を共有する時間の中に、キャリア教育は自然に存在しています。
たとえば、「今日はどんなことが楽しかった?」「そのときどんな気持ちだったの?」といった何気ない会話も、子どもが自分を知り、振り返る力を育てる一歩です。
保護者のコメントは、そうした日常の関わりを通して、学校とのつながりを深め、より豊かな学びを支える橋渡しのような存在になります。
なぜ親のコメントが求められるの?その背景と意義

学校がコメントを求める理由
先生たちは、子どもたちを学校で見守っていますが、どうしても家庭での姿や、日常の小さな変化には気づきにくいことがあります。
そのため、保護者の視点から寄せられるコメントは、子どもをより多面的に理解するうえで欠かせない情報源となります。
たとえば、家でどんな話をしているか、最近どんなことに興味を持っているかなど、学校では見えない一面を知ることができるのです。
その情報をもとに、先生方は子ども一人ひとりに寄り添った声かけや支援を行いやすくなり、子どもたちにとってもより安心して学校生活を送れる環境づくりにつながります。
このように、家庭と学校がつながることで、より充実した教育のサポート体制が築かれるのです。
家庭からのメッセージが持つ影響力
おうちの人の言葉は、子どもにとって心の支えになります。
たとえ短い一言でも、「見守ってくれている」「信じてくれている」という気持ちはしっかり伝わります。
特に、自分の頑張りに対して肯定的なメッセージをもらうことで、自己肯定感が育まれ、次のステップへのやる気にもつながります。
「うまくいかなかったけど挑戦したことがえらいよ」「毎日こつこつ続けているね」など、結果だけでなく過程を認める言葉も大きな力になります。
こうしたメッセージは、子どもの中にじんわりと残り、自信や安心感として根づいていきます。
子どもを客観的に振り返るツールとしての価値
保護者がコメントを書くとき、自分の子どもを客観的に見つめ直す機会にもなります。
「前は苦手だったことが、こんなにできるようになっていた」「この半年でずいぶん落ち着いて行動できるようになったな」など、ふだんは気づきにくい成長に目を向けるきっかけになります。
また、保護者自身が子どもとどう関わってきたかを振り返る時間にもなり、家庭での関わり方を見直すチャンスにもなります。
キャリアパスポートへのコメントは、子どもだけでなく保護者にとっても、成長の軌跡を確認する貴重な記録として残るものなのです。
キャリアパスポートへの親のコメントの書き方ガイド

コメントの基本構成(導入・具体例・まとめ)
キャリアパスポートへのコメントは、「どう書いていいかわからない」と感じることも多いかもしれませんが、3つのステップに分けることで、やさしくまとめることができます。
- はじめに:1年間や学期を振り返って、全体的な印象を書く。たとえば「この1年でたくさんの成長を感じました」「○○を通じて毎日がんばっていたね」など、子どもの歩み全体に対する感想を入れるとスムーズです。
-
具体的なエピソード:がんばったことや挑戦したことを1つか2つ選んで、できるだけ具体的に書いてみましょう。「学級委員を務めて、責任をもって取り組んでいたね」「苦手だった漢字を毎日練習している姿を見て感動しました」など、子どもにとって印象に残る出来事がおすすめです。
-
まとめ・応援の言葉:これからに期待する気持ちや感謝の気持ちを添えて締めくくります。「これからもあなたらしく、楽しみながらいろいろなことに挑戦してね」「いつも笑顔でいてくれてありがとう。応援しています」など、心が温まる一言で終えるとよいでしょう。
この3つを意識して書くことで、短くても子どもにしっかりと気持ちが伝わるコメントになります。
感謝や励ましの言葉の選び方
子どもの努力や姿勢を肯定する言葉は、とても大きな力になります。
「がんばっていたね」「よく続けたね」「○○にチャレンジした姿がすてきだったよ」など、目に見える成果だけでなく、取り組む姿勢や気持ちを受けとめる表現が効果的です。
さらに、「毎朝きちんと起きて学校に行っているだけでもえらいね」「友だちと協力してがんばっていたね」など、日常の小さな努力にも感謝の気持ちを表すと、子どもにとってうれしいはずです。
避けたい表現・NGワードとは?
- 「○○さんよりできてない」などの他の子との比較はNG。子どもが自信を失ってしまう原因になります。
- 「もっと○○しなさい」「○○しないとだめ」などの命令口調や否定的な言葉は避けましょう。
- 「なんで○○しなかったの?」など、問い詰めるような書き方も気をつけたいところです。
否定的な表現よりも、「これから○○もできるようになるといいね」「今のがんばりがきっと実を結ぶよ」といった前向きなメッセージに言い換えると、子どもにとって励みになります。
子どものやる気を引き出すコツ
コメントには、未来に向けた応援の気持ちを込めると、子どものモチベーションがぐんと上がります。
「これからも応援しているよ」「新しいことにも挑戦してね」「何があっても味方だよ」など、温かく背中を押すような言葉を選びましょう。
また、「あなたならきっとできるよ」「どんなときも見守っているよ」など、信頼の気持ちを表す言葉も、子どもの心に深く響きます。
無理に立派なことを書く必要はありません。
シンプルでも、親としての愛情や応援の気持ちが伝われば、それがいちばんの力になります。
書けない…そんなときに!コメント作成のヒント集

日々の会話や行動からヒントを得る
「最近よく話していたこと」「おうちで頑張っていたこと」を思い出してみましょう。
たとえば、「最近、朝早く起きるようになった」「妹に優しくしていた」「お手伝いをよくしてくれた」など、何気ない家庭での行動が立派な成長の証です。
また、「最近好きな本を何度も読んでいた」「折り紙に夢中になっていた」「絵を描くのが好きになってきた」など、子どもの小さな興味もコメントのヒントになります。
子ども自身が言葉にしていなくても、親がそっと気づいてあげた行動を文章にして伝えることで、「ちゃんと見てくれているんだ」と子どもに安心感を与えることができます。
忙しい親でも使える「3ステップ法」
- 成長したことを書く(例:「1年生になって、自分で準備ができるようになりました」)
- がんばったことをひとつ取り上げる(例:「音読を毎日欠かさずに取り組んでいました」)
- 応援の言葉で締めくくる(例:「これからも、できることをどんどん増やしていこうね」)
このように、ほんの数行でも、子どもにしっかりと気持ちが届くコメントになります。
特に時間がないときでも、3つの視点をベースにして書けば、内容にまとまりが出て、読みやすくなります。
さらに余裕があれば、子どもが喜びそうな言葉を一言添えるだけで、より温かみのある文章になります。
子どもが嫌がるときの対応方法
「ちょっと恥ずかしいな」「そんなこと書かないでよ」と言う子もいます。
そういった場合は、内容を控えめにしたり、やさしい言葉でまとめることを心がけましょう。
たとえば「いつも応援しているよ」や「がんばってるのを知ってるよ」など、短くても前向きで肯定的な言葉を選びましょう。
また、「本人が読まなくても大丈夫」と伝えてあげることで、安心して提出できる子もいます。
無理に書かなくても、子どもが受けとめやすい形でメッセージを伝える工夫が大切です。
学年別・目的別の親のコメント例文集
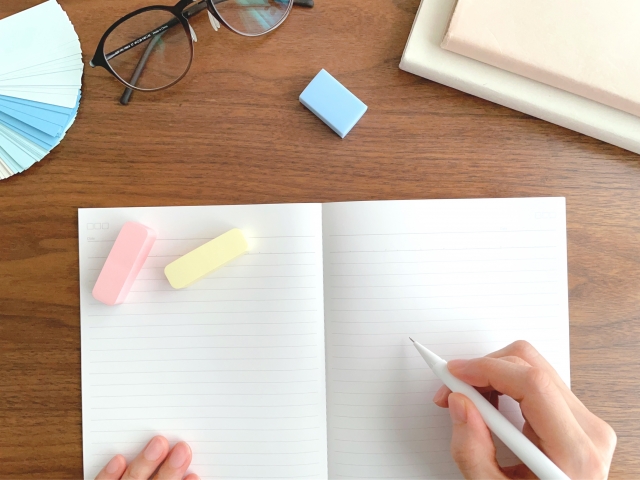
小学1年生向けのコメント例
「初めての小学校生活に、ドキドキしながらもがんばって通っていたね。
おともだちと仲良くできる姿を見て、うれしく思いました。
毎日ランドセルを背負って出かける後ろ姿が、とてもたのもしく感じました。
まだまだ小さなあなたが、大きな一歩を踏み出したこと、本当にえらかったと思います。
これからも、少しずつでいいから、できることを増やしていこうね。」
3年生向けの具体的な例文
「係の仕事をしっかりこなしている姿、すごいなと思いました。
授業中も、手を挙げて自分の意見を伝えたり、友だちの話に耳を傾けたりと、とても落ち着いた姿に成長を感じています。
これからも、自分から行動することを楽しんで、いろんなことにチャレンジしていこうね。」
4年生への応援メッセージ
「いろんなことにチャレンジして、失敗してもあきらめなかったね。
その強さが、とても頼もしいです。
ときには思い通りにいかないこともあったと思うけど、それでもくじけずに前を向いてがんばっていた姿に感動しました。
これからも、自分を信じて、夢に向かって一歩ずつ進んでいこうね。」
中学生・高校生への将来に向けたアドバイス
「自分の考えをしっかり持って行動するようになってきたね。
責任ある立場での活動も増えて、周りへの配慮や協力する姿勢がとてもすばらしいと感じました。
これからも、自分の可能性を信じて、壁にぶつかっても前向きに取り組んでください。
あなたらしい未来が待っていると思います。」
進路に悩む時期の子どもにかける言葉
「迷うこともあると思うけれど、どんな選択でもあなたらしく歩んでいけると信じています。
悩むこと自体が、成長の証です。
まわりの意見も大切にしつつ、自分の気持ちを見つめて、自分らしい道を選んでほしいです。
どんな道を選んでも、あなたを応援していますし、いつも味方です。」
今すぐ使える!コメントテンプレート3選(コピペOK)
① 成長を認めるテンプレート
「○○をがんばって取り組んでいる姿がとても印象的でした。
毎日の積み重ねが少しずつ成果につながっているね。
その姿を見て、とても頼もしく感じました。
これからも、その努力を大切にして、自分に自信を持って歩んでいってね。」
② 努力をほめるテンプレート
「難しいことにも前向きに挑戦する姿を見て、私たちも元気をもらいました。
ときにはうまくいかないこともあったと思うけれど、それでもあきらめずにがんばり続けたあなたの姿がとても立派でした。
がんばり屋さんだね。その努力は、きっとこれからも大きな力になるよ。」
③ 応援メッセージテンプレート
「これからの成長もとても楽しみにしています。
今のがんばりが、未来のあなたをきっと支えてくれるはずです。
どんなことも応援しているよ!
困ったときや迷ったときは、いつでも話してね。
あなたの味方は、いつもそばにいます。」
コメントから見える子どもたちの姿
親が気づいた成長や努力
「知らないうちに、こんなことができるようになっていたんだな」と気づくことは、子育ての中で何度も訪れる感動の瞬間です。
たとえば、ひとりでできることが増えたり、以前は苦手だったことに積極的に取り組むようになったり、友だちと上手に関われるようになったりと、子どもは日々少しずつ成長しています。
コメントを書くという行為は、そんな成長の足あとを振り返るよい機会になります。
「最近は宿題を忘れずにやっているね」「朝、自分で起きて準備ができるようになったね」「お手伝いをしてくれるようになって嬉しいよ」など、何気ない日常にこそ、その子らしい成長が隠れています。
書いていくうちに、ふだん見逃してしまいそうな変化や努力にも気づけるかもしれません。
興味・得意なことを反映させるコツ
「絵が好き」「理科が楽しい」など、子どもの好きなことや得意なことに触れると、その子らしさや個性がよく伝わります。
また、「植物を育てるのが好き」「読書を通していろんな世界に興味をもっている」「ピアノの練習を毎日続けている」など、好きなことに真剣に取り組んでいる姿をコメントに取り入れると、自然体の魅力が伝わります。
学校の勉強だけでなく、家庭での様子や趣味・遊びに対する姿勢も、立派な学びのひとつです。
子どもの内面にある“興味の芽”を見つけて言葉にすることで、本人の自信や意欲にもつながります。
子どもとの絆が深まるコメントとは
「いつも見ているよ」「あなたのことを応援してるよ」という気持ちを込めたコメントは、子どもの心に深く響きます。
そうした言葉が伝わることで、「ちゃんと見てくれている」「自分は大切にされている」と実感でき、親子の信頼関係がより深まります。
ときには、「あなたのがんばりに私も元気をもらっています」「どんなときも、あなたを信じているよ」というような一歩踏み込んだメッセージも、子どもの励みになるでしょう。
愛情を言葉にして伝えることは簡単ではないかもしれませんが、こうした機会を活かして、日ごろの思いを素直に届けることが、親子のつながりをいっそう温かなものにしてくれます。
キャリアパスポートを家庭で活用する方法
親子での振り返りタイムのつくり方
「1年間どうだった?」「どんなことが楽しかった?」と、子どもに聞いてみる時間をつくってみましょう。
できればリラックスした雰囲気で、たとえば夕食のあとやお風呂上がりなど、ふだんの会話に自然に組み込むのがおすすめです。
「がんばったことをひとつだけ教えて」「困ったこともあった?」など、無理のない問いかけからスタートしてみてください。
子どもが話しやすいタイミングを見つけてあげることで、素直な気持ちや印象深い出来事を話してくれることも多くなります。
保護者自身も、「あなたの○○を見ていてうれしかったよ」と振り返りを共有すると、より深い会話につながります。
目標設定のサポートアイデア
「次は○○に挑戦してみたらどう?」と、さりげなく目標を引き出す声かけがポイントです。
子ども自身が「やってみたい」と感じることを一緒に探すような感覚で話すと、自然に前向きな気持ちが生まれます。
たとえば、「○○が得意になってきたね。次はどんなことにチャレンジしてみたい?」といったように、成長を認めながら未来につなげると良いでしょう。
目標が大きすぎると感じるときは、「まずは一週間やってみよう」「少しずつ試してみようね」といった小さなステップに分けてみることも効果的です。
学校との連携・家庭での役割分担
先生との面談でキャリアパスポートの内容を共有することで、よりよいサポート体制が整います。
子どもの学校での様子と家庭での様子をすり合わせることで、子どもへの理解が深まり、支援の方向性が一貫します。
たとえば「最近は○○に興味が出てきました」「家ではこのような話をよくします」といった情報を先生と共有するだけでも、子どもにとって心強い学習環境になります。
また、先生からのフィードバックを家庭での会話に取り入れることで、子どもは一貫したサポートを感じることができ、より安心して成長のステップを踏めるようになります。
知っておきたい!キャリア教育の今と未来
文部科学省が目指すキャリア教育の方向性
文部科学省は、令和の学びの中核として「社会に開かれた教育課程」を推進しています。
これは、子どもたちが自ら考え、判断し、行動できる力を身につけることを重視する教育のあり方です。
その中でキャリア教育は、子どもたちが自分の未来に希望を持ち、主体的に生きていくために欠かせない柱と位置づけられています。
社会の変化が激しい今、自分らしい進路を選び、自立して社会に貢献できる人になるためには、早い段階からのキャリア形成の視点が重要とされています。
キャリア教育は単に職業について学ぶだけではなく、日々の学習や体験を通して「生きる力」を育てることを目的としています。
そのために学校教育では、教科や活動の枠を越えて、子どもの学びを総合的に支えるような取り組みが求められているのです。
非認知能力とコメントのつながり
キャリア教育の中でも注目されているのが、「非認知能力」の育成です。
これは、学力テストなどの数値で表しにくい、人間らしさや社会性に関わる力のことを指します。
たとえば、思いやり、協調性、粘り強さ、自己肯定感、自制心、挑戦する気持ちなどが非認知能力に含まれます。
保護者のコメントは、こうした力を育てるうえで大きな役割を果たします。
「あなたのやさしさに助けられたよ」「最後まであきらめなかったね」などの言葉は、子どもの内面にある価値を認め、育む土台になります。
家庭での日常の様子をふまえて非認知能力に注目したコメントを意識することで、学校だけでは見えにくい子どもの魅力を言語化し、支えることができるのです。
家庭でのキャリア教育はどう進める?
キャリア教育は、決して特別な取り組みではありません。
家庭の中でも、日々の会話や体験の中に自然と存在しています。
「どんなことをしていると楽しい?」「最近気になっていることある?」といった問いかけは、子どもが自分の興味や価値観に気づくきっかけになります。
また、休日に料理や買い物を一緒にしたり、地域のイベントに参加したりすることも、社会とのつながりを感じる立派なキャリア教育です。
家庭では、子どもが自分の気持ちを安心して話せる環境づくりが何より大切です。
そのうえで、子どもの「好き」「得意」「やってみたい」を温かく受けとめていくことで、キャリア形成の土台が育っていきます。
まとめ|親のコメントは“応援メッセージ”というギフト
キャリアパスポートへのコメントは、決して難しく考えすぎなくても大丈夫です。
大切なのは、子どもを見守っているよという「気持ち」を届けること。
その言葉は、きっと子どもにとって一生の宝物になります。
どうか、あなたのやさしい言葉で、お子さんをあたたかく応援してあげてくださいね。